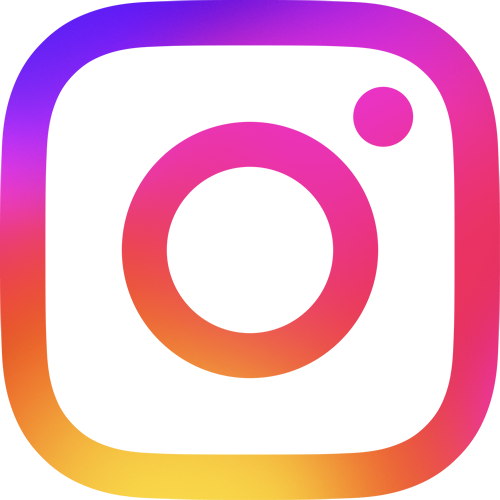遺品整理を進めたいけれど、「どれくらいの日数がかかるのか」「どの時期に始めるのがいいのか」と悩む人は少なくありません。部屋の広さや遺品の量、遺族の人数、業者への依頼方法などによって所要期間は大きく変わります。
この記事では、一般的な遺品整理にかかる期間や作業時間の目安、早く進めるためのコツをわかりやすく解説します。自分たちで行う場合と業者に依頼する場合の違いも紹介しているので、無理のないスケジュールを立てる参考にしてください。
目次
遺品整理にかかる日数の目安とは

遺品整理にかかる日数は、部屋の広さや荷物の量、作業を行う人数によって大きく異なります。1Kや1DKなどの単身世帯であれば半日〜1日ほどで終わるケースもありますが、3LDK以上の家や長年暮らしていた実家となると、3〜5日かかることも少なくありません。自分たちで進める場合と、専門業者に依頼する場合とでは、かかる期間に違いが生じます。
遺品整理の平均的な期間と作業時間
遺品整理の平均的な作業時間は、一般的に「1部屋あたり4〜6時間」が目安とされています。ワンルームのような単身世帯なら1日以内に終わることが多く、2LDK前後の広さになると2〜3日ほどかかります。
ただし、作業内容によっては大きく変動します。仕分けや貴重品確認、供養の有無、清掃作業などを含む場合は、さらに時間を要することがあります。特に家族が立ち会いながら行うケースでは、思い出を振り返る時間も生まれるため、気持ちの整理を優先して進めると全体で3〜4日かかることもあります。
業者に依頼する場合は、作業スタッフが複数人で同時に作業するため、同じ物量でも1日で完了するケースがあります。作業前に工程を確認しておくと、無理のない日程を立てやすくなります。
間取り・遺品量による日数の違い
間取りや荷物の量によって、必要な日数は大きく異なります。荷物の少ない1Kや1DKでは半日〜1日、2LDKでは2〜3日、3LDK以上の広い住宅では3〜5日が一般的な目安です。
荷物の量だけでなく、細かい仕分けが必要な場合や、大型家具・家電が多い場合も時間がかかります。とくに長年暮らしていた実家などでは、押し入れや倉庫などに想定以上の荷物があることが多く、作業が想定より長引くこともあります。
整理を始める前に「どの部屋をどこまで片づけるか」を決めておくと、作業を分割しやすくなります。作業範囲を区切って少しずつ進めることで、体力的にも精神的にも負担を減らすことができます。
自分で行う場合と業者依頼時の比較
自分たちで遺品整理を行う場合、思い出を振り返りながら進められる一方で、作業ペースがゆっくりになりやすく、数日〜数週間かかることがあります。休日中心で作業する場合、1日2〜3時間ずつの作業を何回かに分けて行うのが現実的です。
一方、業者に依頼する場合は、仕分け・搬出・処分までを一括で任せられるため、全体で1〜3日ほどで完了するケースが多くなります。複数人のスタッフが同時に作業を進めるため、効率的に進むのが特徴です。
ただし、業者によって対応範囲やスピードが異なるため、事前に見積もり時点で「作業人数」「所要日数」「追加費用の有無」を確認しておくことが大切です。自分たちの都合や希望に合う形で依頼することで、時間と気持ちの両面で負担を減らせます。
遺品整理の日数は状況によって変わる
遺品整理にかかる日数は、家の広さや荷物の量だけでなく、暮らしていた状況や家族構成によっても大きく異なります。空き家や遠方の実家などは、移動や日程調整が必要となるため、思っている以上に時間を要する場合があります。
ここでは代表的なケース別に、整理完了までのおおよその目安を紹介します。
一人暮らし・実家・空き家などケース別の目安
遺品整理にかかる日数は、暮らしていた環境や住居形態によって大きく変わります。
一人暮らしの部屋(1K・1DK)であれば、荷物の量が少ないため半日〜1日で完了するケースが多くなります。
一方、家族が暮らしていた実家では、家具や衣類、思い出の品が多く、平均で2〜4日程度を見込んでおくのが現実的です。空き家の場合は、家具の撤去や清掃作業が必要になることもあり、3〜5日ほどかかるケースも少なくありません。
住居の状態や遺族の立ち会い有無によっても時間は変動するため、事前に作業日程を決めておくと安心です。余裕を持ったスケジュールを組むことで、無理なく進められます。
遺品の量・家財の種類による違い
遺品整理では、荷物の「量」と「種類」が日数に大きく影響します。
衣類や書類、小物類など細かい物が多い場合は、仕分けや確認作業に時間を要するため、想定以上に日数がかかることがあります。
逆に家具や家電など大型の物が中心なら、搬出作業がメインとなるため比較的スムーズに進みます。
趣味のコレクションや骨董品などが多い家庭では、価値の確認や買取査定のために1〜2日余分に見ておくとよいでしょう。
あらかじめ「分別担当」「搬出担当」など役割を分けて進めると効率的で、作業の停滞を防ぐことができます。
遠方から整理する場合にかかる期間
遠方の実家や空き家を整理する場合は、移動時間や宿泊日程の調整が必要となるため、通常より日数がかかる傾向にあります。
1回の帰省で完了を目指すなら、現地滞在を2〜3日確保しておくと安心です。1〜2回で終わらせたい場合は、事前に業者へ鍵を預けておく方法もあります。
また、不動産の立ち会いや退去手続きなど他の予定と重なることもあるため、整理以外の時間も考慮して計画を立てましょう。
無理なスケジュールを組むと心身に負担がかかるため、必要に応じて業者へ部分的な作業を依頼するのも現実的な選択といえます。
遺品整理を始める前に知っておきたい準備期間
遺品整理は思い立ってすぐに始められるものではありません。親族間での話し合いや必要書類の確認など、事前に整えておくべき準備がいくつかあります。この段階を丁寧に行うことで、実際の作業をスムーズに進められ、全体の日数を短縮することにつながります。
遺族間で話し合うべき内容
遺品整理を始める前に、まず家族や親族の間で整理の進め方を明確にしておくことが大切です。誰が中心となるのか、どの範囲まで片づけるのかを共有しておくことで、後のトラブルを防げます。
特に形見分けや相続に関する部分は、感情が絡みやすく意見が分かれることもあります。そのため、全員が納得できる形でルールを決めておくと安心です。
また、故人の意向が残っている場合は、それを尊重した形で整理を進めることも重要になります。意見が食い違った際は、無理に結論を急がず、いったん保留にするなど柔軟な対応を心がけましょう。話し合いを丁寧に行うことで、作業の段取りが明確になり、結果的に作業日数を短縮できます。
必要な書類や手続きの確認
遺品整理をスムーズに進めるためには、各種書類や契約関係を事前に確認しておくことが欠かせません。公共料金や保険、年金、金融機関などの書類は誤って処分しないよう、保管場所を家族で共有しておくと安心です。
特に賃貸物件では、退去日や解約手続きの期限を確認し、遺品整理のスケジュールと重ならないようにしておく必要があります。これを怠ると、延長費用やトラブルにつながることもあります。
また、相続や税金に関わる重要書類が混ざっていることも多いため、「重要」「確認済み」などラベルを付けて分類しておくと見落としを防げます。準備を整えておくことで、当日の作業を効率よく進められるだけでなく、手続き面での負担も減らせます。
遺品整理の日数が長くなる主な理由

遺品整理が予定より長引くことは珍しくありません。特に家族だけで進める場合や、思い出の品が多い家庭では時間がかかる傾向があります。
ここでは、作業が長引く主な理由を挙げながら、どのように対策できるかを考えていきます。
仕分けや確認に時間がかかるケース
遺品整理では、写真や手紙、記念品など思い出の詰まった品を一つひとつ確認しながら進めるため、どうしても時間がかかります。「残す」「処分する」の判断に迷うことも多く、感情的な整理がつかないまま作業が止まってしまうケースもあります。
また、貴重品や重要書類を探す場合も慎重さが求められるため、短時間で終わるとは限りません。特に、通帳や印鑑、土地関係の書類などが複数の部屋に分散している場合は、思った以上に時間を要します。
事前にチェックリストを作り、探すものを明確にしておくと、確認漏れを防ぎながら効率よく進められます。感情面の整理を優先したいときは、作業を数日に分けて進めるのも一つの方法です。
遺族の予定調整や立ち会いの必要性
家族がそれぞれ仕事や生活の都合を抱えている場合、全員の予定を合わせるだけでも時間がかかります。とくに遠方に住む家族がいる場合は、交通手段や宿泊の調整も必要になり、思うように作業が進まないこともあります。
また、業者へ依頼する場合でも、立ち会いが必要な作業をどの日に行うかを調整しなければなりません。スケジュールが重なると希望日に作業が入れられず、結果的に数日延びることもあります。
予定を共有するために、家族で共有カレンダーを活用する方法も有効です。早めに全員のスケジュールを確認しておくことで、作業日を確保しやすくなり、無理のない進行につながります。
処分・買取・供養などの工程が多い場合
遺品整理は、単なる片づけではなく、処分・買取・供養といった複数の工程を含むことが多くあります。仏壇や人形、写真などは供養を希望されるケースが多く、その分だけ時間を要します。買取査定を依頼する場合も、査定日や引き取り日を業者と調整する必要があり、スケジュールが延びる原因になります。
特に、複数の業者へ別々に依頼している場合は、連絡の手間や日程のズレが生じやすく、全体の作業が長引く傾向にあります。これらを一括で対応できる業者を選ぶと、作業全体を効率よく進められます。
作業内容を事前に整理し、どの工程を業者に任せるかを明確にしておくことで、余計な日数をかけずにスムーズに完了させることができます。
遺品整理を早く終わらせるための工夫
遺品整理は、段取りや準備を工夫することで大きく時間を短縮できます。事前に分別のルールを決めておくことや、業者との打ち合わせをしっかり行うことが大切です。作業の流れを整理しておくことで、無駄な動きを減らし、気持ちにも余裕を持って取り組むことができます。
- 事前に分別ルールを決めておく
- 業者との打ち合わせを効率的に進める
- 不用品回収や買取サービスを併用する
上記のポイントを意識しておくと、作業が重なってもスムーズに整理を進められます。それぞれの工夫について具体的に解説していきます。
事前に分別ルールを決めておく
整理を始める前に、「残す」「譲る」「処分する」といった分類基準を家族で共有しておくと、判断がスムーズになります。あらかじめルールを決めておけば、迷う時間を減らせるため、全体の作業日数を短縮できます。特に思い出の品は感情が伴うため、ルールがあることで気持ちの整理にもつながります。迷ったものは「保留箱」に入れ、後日改めて見直すのも有効です。
業者との打ち合わせを効率的に進める
業者に依頼する場合は、見積もり時に作業範囲と日数の目安を明確にしておくことが大切です。作業前に現地を確認してもらい、搬出経路や分別方針を共有しておくと、当日の作業がスムーズになります。特に複数業者で比較している場合は、対応体制やスタッフ数も確認しておくと安心です。細かい点も遠慮せず質問しておくと、誤解を防ぎつつ予定通りに進められます。
不用品回収や買取サービスを併用する
遺品整理では、すべてを処分するよりも、リサイクルや買取を上手に取り入れることで手間を減らせます。家具や家電、貴金属などは買取サービスを利用すると、費用面の負担も軽減できます。不用品回収業者と遺品整理業者を組み合わせる方法もあり、スケジュール調整がしやすくなる点がメリットです。分別から搬出までを一括で任せられる業者なら、全体の作業期間を1〜2日ほど短縮できます。
作業日数を短縮できる遺品整理業者の選び方
遺品整理をスムーズに進めるには、信頼できる業者選びが重要です。特に作業日数を短縮したい場合は、スタッフ数や対応範囲などの「スピード力」に注目する必要があります。見積もり時にしっかり確認しておくことで、予定通りに完了できる可能性が高まります。
スタッフ数や対応体制を確認する
作業を担当するスタッフの人数によって、かかる時間は大きく変わります。複数名体制で一斉に作業できる業者なら、1〜2日で完了することもあります。反対に、少人数での対応だと、3日以上かかるケースもあるため、契約前に人数を確認しておくことが大切です。また、急な追加作業にも柔軟に対応できる体制があるかもチェックしましょう。
見積もり時に作業工程と日程を具体的に聞く
見積もり時には「作業開始から完了までのスケジュール」を明確にすることがポイントです。搬出や清掃、供養の有無など、各工程の所要時間を具体的に聞いておくと、後からのズレを防げます。口頭だけでなく、見積書や工程表で確認できる業者を選ぶと安心です。納得できるまで説明を受けることで、作業全体の流れを把握しやすくなります。
供養・買取などワンストップ対応の業者を選ぶ
遺品整理の中には、供養や買取、ハウスクリーニングなど複数の作業を伴うことが多くあります。それぞれ別の業者に依頼すると日数が延びるため、ワンストップで対応できる業者を選ぶと効率的です。1社でまとめて依頼することで連携ミスが減り、作業日数を短縮できます。事前に対応範囲を確認し、信頼できる専門業者に依頼することが大切です。
遺品整理に適した時期と注意点

遺品整理の時期は、気候や家族の予定、物件の契約状況によっても最適なタイミングが異なります。無理に急ぐよりも、心と体に負担をかけずに取り組める時期を選ぶことが大切です。
ここでは整理に適した時期と、注意すべき点を紹介します。
気候やスケジュール面で無理のない時期を選ぶ
春や秋など気候が穏やかな季節は、作業がしやすく、体力的な負担も少なくなります。夏は熱中症のリスクが高く、冬は日照時間が短いため、時間配分に注意が必要です。また、仕事や家族の予定が重ならない時期を選ぶことで、焦らず進められます。気候や予定を考慮してスケジュールを組むと、心にも余裕を持てるでしょう。
年末や繁忙期に依頼する際の注意点
年末や連休明けなどの繁忙期は、遺品整理業者への依頼が集中します。そのため希望日に予約が取れないこともあるため、早めの問い合わせが大切です。また、料金が繁忙期価格になる場合もあるため、複数社で見積もりを比較しておくと安心です。予定を立てる際は、余裕を持ったスケジュール設定を意識しましょう。
まとめ
遺品整理にかかる日数は、部屋の広さや荷物の量、作業方法によって大きく異なります。1Kなら半日〜1日、2LDKで2〜3日、3LDK以上では3〜5日を目安に考えるとよいでしょう。自分たちで行う場合は、仕分けや確認に時間がかかりやすいため、早めに準備を始めることが大切です。
また、気候が穏やかな時期や家族の予定が合うタイミングを選ぶことで、心身への負担を減らせます。業者に依頼する際は、スタッフ体制や作業工程、対応範囲を事前に確認しておくと安心です。
焦らず計画的に進めることで、時間の負担を軽減できるだけでなく、心の整理にもつながります。
もし「どのくらいの日数で終わるかわからない」「自分たちだけでは難しい」と感じたときは、専門の遺品整理業者に相談してみてください。
遺品整理のエンドロールでは、現場の状況やご家族の希望に合わせて最適な作業日程とプランをご提案しています。無理のないスケジュールで整理を進めたい方は、まずはお気軽にご相談ください。