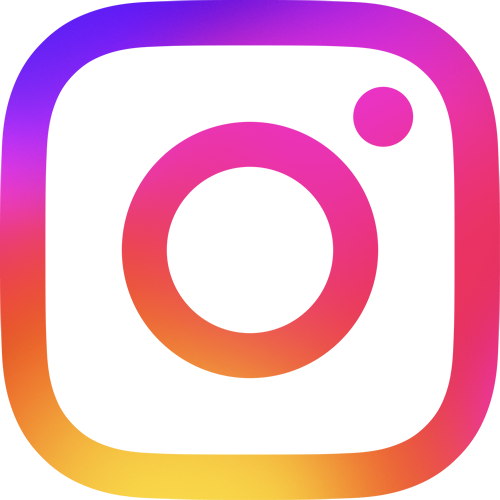身内の突然の死や孤独死など、想定外の出来事が起きたあとに「部屋の片付けをどうすればいいのか分からない」と悩む人は少なくありません。一般的な掃除では対応が難しい場合、遺体の痕跡や臭気、害虫の発生を取り除くために行われるのが「特殊清掃」です。通常の清掃とは異なり、専門知識と防護装備を備えた業者が対応する必要があります。
この記事では、特殊清掃の基本的な内容や依頼できる作業の範囲、費用相場、依頼の流れをわかりやすく解説します。特殊清掃を検討している方や、どのようなケースで必要になるのか知りたい方はぜひ参考にしてください。
目次
特殊清掃とはどんな作業を指す?

特殊清掃とは、事故死・孤独死・自殺などの現場で、通常の掃除では除去できない血液・体液・臭気・害虫などを専門的に処理する清掃のことを指します。感染防止や臭気除去など専門的な対応が必要となるため、資格や経験を持つ清掃員が専用の薬剤や防護具を使って作業を進めます。
一般清掃との違いと作業目的
一般清掃は、部屋の見た目をきれいに整えたり、埃や汚れを落としたりすることを目的としています。一方で特殊清掃は、事故や孤独死などで発生した体液・血液・臭気を除去し、衛生的に安全な環境へと戻すことを目的とします。
作業では、感染症の原因となる細菌やウイルス、臭気の元となる有機物を専用薬剤で分解・除去します。さらに、オゾン脱臭機やバイオ消臭剤などを使い、建材や空気中に残った臭気成分まで徹底的に取り除きます。
単に「汚れを落とす」というレベルではなく、'安全と衛生の再生を目的とする専門作業'である点が一般清掃との大きな違いです。また、清掃にあたるスタッフは感染防止のため防護服・マスク・手袋を着用し、作業区域を区切りながら慎重に進めます。こうした工程を経て、再び人が入れる空間へと整えるのが特殊清掃の役割となります。
特殊清掃が必要になる主なケース
特殊清掃が求められるのは、孤独死や事件・事故などの現場だけではありません。時間の経過により体液や臭気が建材へ染み込んだり、害虫が繁殖したりする場合にも対応が必要になります。
たとえば、ペットの多頭飼育崩壊やゴミ屋敷化が進行した住宅では、悪臭やカビの繁殖により健康被害が出ることもあります。また、火災や水漏れ後の建物で有害物質が残留しているケースも、特殊清掃に含まれます。
このような現場では、一般的な掃除では臭いの根源や菌を完全に除去できません。放置すると建物の劣化や感染症の原因となるため、早めの専門対応が重要です。現場の状況に応じて、除菌・脱臭・廃棄物処理などを組み合わせることで、安全に生活できる環境を取り戻すことができます。
特殊清掃で対応できる主な作業内容
特殊清掃は単なる清掃作業にとどまらず、除菌・脱臭・汚染物撤去・原状回復まで幅広く対応します。現場の状態によって必要な作業は異なりますが、いずれも安全性と衛生面を確保するために重要な工程となります。
消臭・除菌・害虫駆除
特殊清掃では、最初に臭気や感染源を取り除くための除菌・消臭作業を行います。時間の経過とともに発生した腐敗臭や体液臭は、壁や床材の奥深くまで浸透していることが多く、一般的な清掃では完全に除去できません。そのため、オゾン脱臭機やバイオ消臭剤を使い、臭気成分そのものを分解します。
また、腐敗に伴い発生したハエやウジ、ゴキブリなどの害虫は感染症の媒介となるため、駆除作業も同時に進めます。薬剤を散布する際は、近隣への影響を考慮して適切な換気と安全管理を行うことが重要です。作業を丁寧に進めることで、再発防止にも効果を発揮し、清潔で安全な空間へと戻せます。
汚染物や遺品の撤去
特殊清掃では、血液や体液が染み込んだ布団・衣類・家具などの汚染物を専門的に分別し、安全な手順で撤去します。感染防止のため、防護服・手袋・マスクを着用したうえで、自治体の基準に沿って処理することが求められます。
作業の際は、遺族の意向を尊重しながら「残すもの」と「処分するもの」を丁寧に仕分けます。感情面への配慮が必要な現場も多く、経験豊富な作業員によるコミュニケーションが欠かせません。撤去後は床や壁の清掃・除菌まで行い、残留した臭気や菌を防ぐことで、衛生的に安心できる空間へと整えます。
作業にかかる時間の目安と注意点
作業にかかる時間は、現場の広さや汚染の程度によって異なります。1R〜1Kであれば半日から1日ほどが目安となりますが、臭気が強い場合や建材の交換が必要な場合には、数日かかることもあります。
作業中はオゾン処理や薬剤散布を行うため、周囲への臭気拡散を防ぐ対策が欠かせません。作業中に立ち入ると健康被害のおそれがあるため、清掃中は関係者以外の立ち入りを避けるようにします。依頼前に、作業時間・使用機材・安全対策などを業者としっかり確認しておくと安心です。明確な説明をしてくれる業者であれば、信頼して任せることができます。
原状回復やリフォームのサポート
特殊清掃の完了後は、必要に応じて原状回復やリフォームを行い、入居可能な状態に整えます。床材や壁紙の交換、再塗装、畳の張り替えなどを行うことで、臭気や汚れを完全に取り除くことができます。特に臭気が建材に染み込んでいる場合は、部分補修だけでなく全体の張り替えが必要になることもあります。
清掃とリフォームを一括で対応できる業者に依頼すると、工程が短縮できるうえに費用の見通しも立てやすくなります。仕上がりを確認しながら少しずつ復旧を進めることで、再利用や再入居の計画が立てやすくなります。環境を整えることは、心の整理にもつながる大切な工程です。
特殊清掃にかかる費用相場

特殊清掃の費用は現場の状況や作業内容によって大きく変わります。汚染の範囲や臭気の強さ、部屋の広さなどが料金に影響します。また、消臭機材や廃棄物処理の有無など、追加作業によっても費用が前後します。
ここでは、一般的な相場と見積もり時に意識したいポイントを整理します。
部屋の状態別の料金目安
特殊清掃の費用は、1Rや1Kでおおよそ5万〜15万円が目安となります。腐敗が進行している場合や汚染が広範囲に及ぶケースでは、20万円を超えるケースも見られます。作業には防護服・専用薬剤・オゾン脱臭機などの機材費が含まれており、臭気除去や感染対策を徹底するほど費用が上がります。さらに、遺品整理やリフォームを併せて依頼する場合は、合計で30万〜50万円程度になることもあります。
追加費用が発生するケース
見積もり時の想定外により、追加費用が発生するケースもあります。代表的なものとしては、次のような内容が挙げられます。
- 床下や壁内部にまで体液が浸透していた場合の追加清掃
- 臭気除去を強化するためのオゾン脱臭作業の追加
- 害虫駆除や除菌処理の範囲拡大
- 大量の廃棄物が見つかった場合の回収費用
現地調査の段階で汚染範囲が正確に確認できない場合、作業途中で追加作業が必要になることもあります。あらかじめ「どの範囲までは基本料金に含まれるのか」を確認しておくことが大切です。
見積もり時に確認しておくべき項目
見積もりを依頼する際は、料金だけでなく内訳の透明性を重視することが重要です。確認しておくと安心な項目として、次のようなポイントが挙げられます。
- 作業内容の範囲(清掃・脱臭・除菌・廃棄物処理など)
- 使用する薬剤や機材の種類
- 交通費や駐車料金、出張費の有無
- 追加費用が発生する条件
見積もり時に不明点をそのままにしておくと、作業後にトラブルへと発展するおそれがあります。複数の業者から見積もりを取り、料金だけでなく対応の丁寧さや説明のわかりやすさも比較すると安心です。
特殊清掃を依頼するまでの流れ
初めて特殊清掃を依頼する際は、どのような手順で進むのかを理解しておくと安心です。多くの業者は、問い合わせから現地調査・見積もり・契約・作業・確認の流れで対応します。
ここでは、実際の進行手順を段階的に説明します。
見積もり依頼と現地調査
まずは電話やメールで現場の状況を伝え、業者に見積もりを依頼します。その後、専門スタッフが現地調査を行い、汚染の範囲や臭気の強さを確認します。現地調査を経て初めて正確な費用が算出されるため、写真や状況を正確に伝えることが大切です。調査時には、立ち入り制限区域を設けるなど安全確保にも配慮されます。
作業内容の確認と契約
見積もりの内容に納得できたら、正式に契約を行います。契約前には、作業範囲・所要時間・使用薬剤・追加料金の有無を再確認しておきましょう。契約書に不明点がある場合はそのまま署名せず、現場責任者に説明を求めることが大切です。信頼できる業者であれば、質問に丁寧に答え、リスクや制限もきちんと伝えてくれます。
清掃後の消臭確認と引き渡し
作業が完了すると、担当者が現場を最終確認し、臭気の残留や汚れの有無をチェックします。必要に応じて再脱臭を行い、消臭効果が確認できた時点で引き渡しとなります。引き渡し後も臭いが気になる場合は、再度点検を依頼できるアフターサービスを利用すると安心です。信頼できる業者は、作業後の報告書やビフォーアフター写真を提示してくれることが多く、品質の高さを確かめられます。
特殊清掃業者を選ぶ際のポイント
特殊清掃は高い専門性が求められる作業であり、業者の技術や信頼性によって結果が大きく変わります。
ここでは、依頼時に確認したいポイントと注意すべき点を紹介します。
資格や許可を持つ専門業者かどうか
特殊清掃を安全に行うためには、法律で定められた許可や専門資格が必要になります。具体的には、感染性廃棄物を適切に処理するための「一般廃棄物収集運搬業」または「産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っていることが重要です。これらの許可がない業者が清掃や廃棄を行うと、法令違反になるおそれがあります。
さらに、作業員が「事件現場特殊清掃士」や「遺品整理士」といった専門資格を取得している業者は、知識・技術・倫理面でも信頼性が高いといえます。資格の有無や作業実績は、ホームページや見積もり時に確認しておくと安心です。安全な作業を徹底しているかどうかが、仕上がりの品質にも大きく関わります。
見積もり内容の透明性と対応力
見積もりの内容が明確で、作業の流れを丁寧に説明してくれる業者は信頼できます。信頼できる業者ほど「作業範囲」「使用する薬剤」「追加費用が発生する条件」などを具体的に提示し、質問にも誠実に答えてくれます。
また、作業中に予期せぬ状況が発生した場合でも、勝手に進めるのではなく、追加作業の理由や費用を必ず説明したうえで了承を得てから作業を進めるのが一般的です。逆に、曖昧な見積もりや強引な契約を迫るような業者は注意が必要です。作業前のやり取りで対応の丁寧さを感じられる業者を選ぶことが、最終的な満足度にもつながります。
悪質な特殊清掃業者を見分けるコツ
特殊清掃の需要が増える一方で、無資格で営業する業者や、相場より極端に安い見積もりを提示して契約を急がせる悪質業者も存在します。こうした業者の中には、作業後に高額な追加費用を請求したり、適切な消臭・除菌を行わずに引き渡すケースもあります。
見分けるポイントとしては、まず「許可番号の有無」「見積もり内容の明確さ」「口コミや実績の確認」が挙げられます。信頼できる業者は作業写真や報告書を提示し、作業の透明性を保っているのが特徴です。加えて、自治体や警察、福祉関連機関から紹介される業者であれば信頼度はより高いといえます。安心して任せられる業者を見極めることが、後悔のない依頼につながります。
特殊清掃と併せて考えたい遺品整理・原状回復

特殊清掃が必要な現場では、遺品整理や原状回復を同時に行うケースも少なくありません。汚染物の除去や脱臭を終えたあとに、家具や家財の整理を進めることで、心の整理にもつながります。
ここでは、特殊清掃と遺品整理を併せて依頼するメリットや、原状回復の重要性を解説します。
遺品整理との違いと連携のメリット
特殊清掃は主に衛生的な処理を目的とする一方、遺品整理は残された品を分類・仕分けし、必要なものを残す作業を指します。両者を同時に行うことで、清掃後の片付けがスムーズに進み、再び部屋を使える状態へと整えることができます。特に孤独死現場などでは、故人の遺品に汚染が及んでいることも多く、清掃と仕分けを並行して行うことで安全に作業を進められます。遺族の意向を尊重しながら丁寧に対応できる業者を選ぶことが大切です。
原状回復やリフォームまで依頼する場合
特殊清掃後に原状回復やリフォームを行うことで、再び入居や賃貸契約が可能な状態に戻せます。壁紙の貼り替えやフローリング補修、塗装などを行い、臭気や汚れを完全に取り除くことで、周囲への影響を防ぐことにもつながります。清掃とリフォームを一括で依頼できる業者を選べば、費用や日程の調整がしやすく、手間も抑えやすくなります。清掃後の状態を確認しながら、必要な範囲で復旧を進めるのが理想です。
まとめ
特殊清掃とは、通常の掃除では対応できない汚染や臭気を除去し、再び安全に生活できる環境を整えるための専門作業です。孤独死や事故など想定外の状況に直面すると、どう対処してよいか分からなくなることもありますが、専門業者に依頼することで衛生面・心理面の負担を大きく軽減できます。費用や作業内容、業者選びのポイントを理解しておくと、より安心して依頼に踏み出せます。
もし「どこに頼めばよいか分からない」「遺品整理も一緒に相談したい」と感じている場合は、遺品整理のエンドロールにご相談ください。特殊清掃や遺品整理、原状回復までを一括でサポートし、経験豊富なスタッフが一つひとつ丁寧に対応します。話を聞くだけでも不安が和らぐことがありますので、無理のない範囲で専門家に相談してみるのがおすすめです。